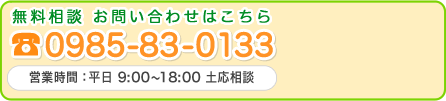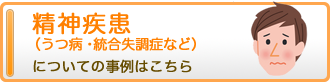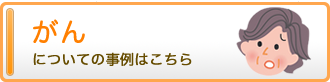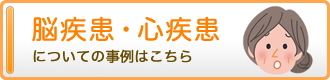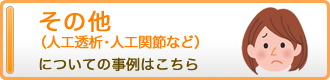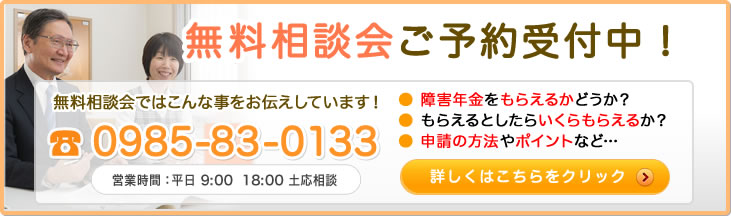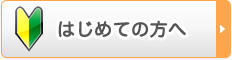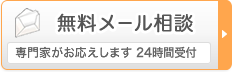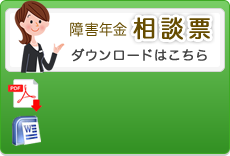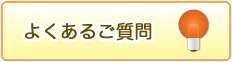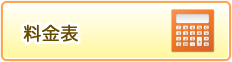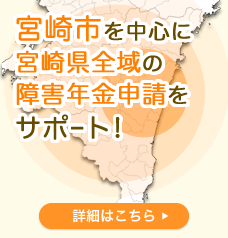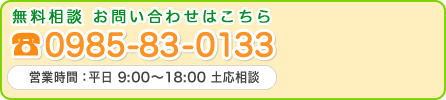当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例
障害年金と傷病手当金の支給調整について
こんにちは。宮崎障害年金センターです。今回は障害年金と傷病手当金の支給調整についてお伝えいたします。
1.障害年金と傷病手当金の違い
傷病手当金は病気やケガによって、「仕事をすることが出来ない」人を対象にしています。しかし、1年6ヶ月という期間限定の給付のため病気やケガが治ったかどうかにかかわらず、1年6ヶ月経過した時点で支給停止になってしまいます。
一方、障害年金は1年6
続きを読む >>
うつ病で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース
相談者
相談者:女性/無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約142万(年間受給額:約78万 遡及額:なし)
相談時の相談者様の状況
H16年2月頃から就職のことで悩むようになり、同年3月頃から不眠、食欲低下、情動不安定、イライラ、動悸等が出現するようになり、精神科を受診されました。
しかしその後就職先でのパワハラ等により症状
続きを読む >>
年末年始のお知らせ
こんにちは。宮崎障害年金センターです。
誠に勝手ながら下記のとおり、年末年始を休業とさせて頂きます。
期間中、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、
どうかご了承くださいますようお願い申し上げます。
2017年12月29(金)-2018年1月3日(水)
※1月4日(木)より通常通りに営業を再開いたします。
どうぞ良いお年をお迎えください。
続きを読む >>
【宮崎市】クローン病で障害厚生年金2級を取得、年間約107万円を受給できたケース
相談者
相談者:女性/無職
居住地:宮崎市
傷病名:クローン病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約322万(年間受給額:約107万 遡及額:なし)
相談時の相談者様の状況
S63年頃から原因不明の腹痛と発熱が続くようになり、H1年8月に内科を受診したところ、その
時は潰瘍性大腸炎と診断されました。しかしその後も投薬治療にもかかわらず症状は改
続きを読む >>
【宮崎市】視神経萎縮で障害厚生年金2級取得、年間約123万円を受給できたケース
相談者
相談者:男性(30代)/会社員
居住地:宮崎市
傷病名:視神経萎縮
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約205万(年間受給額:約123万、遡及額:なし)
相談時の相談者様の状況
H28年2月頃から視力低下及び視野狭窄が顕著となり、H28年2月に眼科を受診しました。そこ
では原因不明の視神経萎縮と診断され眼鏡を処方されましたが、有効な治
続きを読む >>
【宮崎市】脳梗塞で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース
相談者
相談者:男性(50代)/自営業
居住地:宮崎市
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約290万(年間受給額:78万 遡及額:270万)
相談時の相談者様の状況
AさんはH24年8月に自宅で脳梗塞で倒れ、大学病院に救急搬送されました。
初診後はH25年1月末までリハビリを続けていました。
相談時(H29年
続きを読む >>
【延岡市】脳梗塞で障害厚生年金2級を取得、年間約166万円を受給できたケース
相談者
男性(50代)/会社員
居住地:延岡市
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約220万(年間受給額:約166万 遡及額:なし)
相談時の相談者様の状況
Eさんは約1年前に自宅にて脳梗塞で倒れ、近医にて初診を受けました。初診後、数ヶ月間リハビリを続けた後相談に来られました。傷病手当金は1年6ヶ月で支給されなくなるので、その後
続きを読む >>
障害年金マンガを掲載しました
障害年金について分かり易くまとめたマンガを掲載しました。
ぜひご一読下さい。
続きを読む >>
2017年8月10日(木)~2017年8月16日(水)まで研修に行ってきます
———————————————————
■休業期間
2017年8月10日(木)~2017年8月16日(水)
———————————————————
2017年8月17日(木) から平常通り営業いたします。
研修中のメールでのお問い合わせに対する回答は、3営業日以内には対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
研修期間中はご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますよう
続きを読む >>
働きながら障害年金はもらえるの?
これは障害年金のご相談で多くの方から受ける質問ですが、
基本的に働いていても「障害の認定基準」を満たせば障害年金は受給することができます。
事実、国のデータでも65歳未満の障害年金受給者のうち、
3割以上の方が障害年金を受給しながら働いているとされています。
ところが昨今とりわけ精神障害の場合、
就労の有無によって判定が大きく左右されるようになり、
未就労の場合に比べて
続きを読む >>